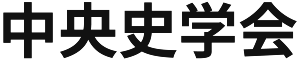- HOME
- 『中央史学』バックナンバー(創刊号~第10号)
創刊号~第10号(昭和52年~昭和62年)
創刊号昭和52年10月
巻頭言 橋本克彦(1)
論文
| 糸割符仕法の起源 中田易直 |
(3) |
| 近世初頭長崎奉行の一考察 清水紘一 |
(26) |
| 明治初期地方政治の一形態―明治二年の京都会議について― 沖田哲雄 |
(47) |
研究ノート
| 鎖国成立期日朝貿易に関する一史料 田代和生 |
(64) |
| 「田中上奏文」その後 稲生典太郎 |
(77) |
書評
| 稲生典太郎著 『条約改正論の歴史的展開』 佐藤元英 『中央史学』会彙報 |
(82) |
| 成立の経過 |
(87) |
| 会則 |
(88) |
| 第一回総会記事 |
(90) |
| 第一回研究発表会要旨 |
(91) |
第2号昭和54年10月
論文
| 近世思想史研究に思う 伊東多三郎 |
(1) |
| 武家社会における加冠と一字付与の政治性について―鎌倉幕府御家人の場合― 紺戸淳 |
(10) |
| 下関講和談判における日本の通商要求について―特に原敬通商局長の意見書を中心として― 堀口修 |
(27) |
研究ノート
史料紹介
書評
| 千田稔・松尾正人共著 『明治維新研究序鋭―維新政権の直轄地―』徳川慶喜公伝輪読会 |
(59) |
第3号昭和55年3月
論文
| 伝教大師最澄の生年について―嗣永芳照氏鋭及び諸史料の再検討― 飯田瑞穂 |
(1) |
| 幕末・維新期における砥石業の検討―上州砥石業史の序として― 小山 博 |
(25) |
研究ノート
| 『山城国山科郷古図』の成立と伝来 寺嶋雅子 |
(47) |
| 鎌倉時代鶴岡八幡宮に関する基礎的考察 外岡慎一郎 |
(67) |
| 北信濃における国人の動向―市河氏の所領形成を中心として― 山岸啓一郎 |
(84) |
史料紹介
| 東亜勧業株式会社設立に関する駒井徳三の二つの意見書 佐藤元英 |
(99) |
第4号昭和56年8月
論文
| 松前藩における問屋制度の特質について 菊地義美 |
(1) |
| 明治初期太政官制度と左院 松尾正人 |
(13) |
| 鎌倉末期葛川の荘民構成について 坂田 聡 |
(36) |
| 江戸時代の金銀貨在高について 林 定吉 |
(60) |
書評
紹介
| 山本四郎編『第二次大隈内閣関係史料』 佐藤元英 |
(87) |
歴史教育
第5号昭和57年3月
論文
| 摂関家と天神信仰 並木和子 |
(1) |
| 鎌倉期における鎌倉の番匠について 後藤正吉 |
(19) |
| 松方日田県政下における農民一揆―日田・玖珠両郡一揆を中心として― 池田 宏 |
(35) |
研究ノート
| 円満寺旧蔵弘福寺文書をめぐって 松田和晃 |
(57) |
| 『明文抄』所引の「三代の格」―『類聚三代格』の逸文と校訂をめぐって― 寒川照雄 |
(75) |
| 天正十五年六月十八日付キリシタン禁令について 平井誠二 |
(86) |
追悼
| 森克己先生追悼 中田易直 |
(100) |
| 森克己先生略年譜 |
(105) |
| 森克己先生主要著作日録 |
(108) |
第6号昭和58年3月
論文
| 詔勅の起草について 三星光弘 |
(1) |
| 東国における荘園・国衙領年貢の幕府請負制について 高橋裕次 |
(18) |
| 近世の樟脳貿易について―オランダ商館の商業帳簿を中心として― 鈴木康子 |
(35) |
| 元文の貨幣改鋳についての一考察―享保十七年の大飢饉の影響と改鋳実施の意図を中心として― 林 定吉 |
(61) |
紹介
| 『堀田正睦外交文書』―千葉県史料 近世編 堀口 修 |
(81) |
第7号昭和59年3月
論文
| 北条貞時政権の研究―弘安末年における北条貞時政権の実態分析― 渡辺晴美 |
(1) |
| 「日清通商航海条約」締結交渉について 堀口 修 |
(21) |
| 留守政府における太政官三院制の変質過程 藤田 正 |
(73) |
研究ノート
| 後北条氏天文の「御国法」について―いわゆる「伊勢宗瑞十七ヶ条」の再検討を中心に― 山口 博 |
(97) |
史料紹介
| 近江国竹生島における神仏分離をめぐる史料 池田 宏 |
(123) |
| 九十九里浜旧地曳網主飯高家「過去交名帳」 齋藤 功 |
(130) |
第8号昭和60年3月
論文
| 藤原行成の神祇信仰について 並木和子 |
(1) |
| 東国御家人渋谷氏の西遷とそれにともなう「惣地頭職」の変質 雉岡恵一 |
(17) |
| 長崎貿易の輸入統制に関する寛文期の二法令 太田勝也 |
(33) |
| 山県内相の欧州視察と府県制・郡制草案の編纂問題 安藤陽子 |
(53) |
研究ノート
| 中世訴訟手続の発展について 山本孝司 |
(71) |
| 江戸小伝馬町牢屋敷における「牢法」の一考察 饗場 実 |
(80) |
第9号昭和61年3月
論文
| 鎌倉期在地領主層における族的結合の構造 岸本光子 |
(1) |
| 寛永18年(1641)の日蘭貿易における「取引」についてム平戸および長崎出島オランダ商館「仕訳帳」の分析 行武和博 |
(21) |
| 元老院の成立―石川県区長総代(忠告社)建白と元老院の機構編成を中心に― 角田 茂 |
(64) |
| 斉藤実内閣における対ソ政策―日ソ不侵略条約問題と五相会議を中心に― 佐藤元英 |
(83) |
研究ノート
| 軍団兵士制に関する若干の問題 武藤浩一 |
(105) |
紹介
| 信夫清三郎著『日清戦争』の発禁処分に関する一外務省資料について 堀口 修 |
(125) |
| 稲生典太郎先生の古稀を祝う 中田 易直 |
(128) |
| 稲生典太郎先生 略年譜・著作日録 |
(131) |
第10号昭和62年3月
論文
| 六国史の祥瑞記事について 柄 浩司 |
(1) |
| 室町時代備後国太田笹の年貫送進と尾道船 佐々木銀弥 |
(21) |
| 肥前青方氏の生業と諸氏結合 白水 智 |
(45) |
| 堺市法貨物商人の実態について 木崎弘芙 |
(69) |
| 東京府下市街地における地租改正 滝島 功 |
(92) |
| 1881年10月の太政官制改革に関する一考察 中川寿之 |
(115) |
研究ノート
| 河内の西大寺末寺と惣墓―西琳寺・教興寺・寛弘寺― 細川涼一 |
(131) |
史料紹介
書評
| 松尾正人著『廃藩置県―近代統一国家への苦悶―』 松崎 彰 |
(151) |
『中央史学』会創立10周年記念行事
| 史学会成立以前のこと 橋本克彦 |
(158) |
| 佐藤進一先生の古稀を祝う 中田易直 |
(163) |
| 佐藤進一自歴略譜 佐藤進一 |
(166) |
PAGE TOP