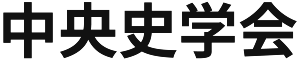- HOME
- (コピー) 『中央史学』バックナンバー(第11号~第20号)
第31号~第40号(平成20年~平成29年)
第31号平成20年3月
論文
| 摂関時代の地方政治 -受領たちのネットワークを媒介として考える- 加藤友康 |
(1) |
| 鎌倉期における陰陽家安倍氏について -安倍晴道党を中心に- 赤澤春彦 |
(17) |
| 宮内省における「明治天皇実録」の編修について -「明治天皇記」との関連に着目して- 堀口修 |
(38) |
研究ノート
| 外務省の「保存記録」と『日本外交文書』編纂事業 佐藤元英 |
(58) |
調査報告
| ハインリッヒ・フォン・シーボルトの業績をたどる調査旅行 -没後100年を迎えて- 関口忠志 |
(80) |
書評
| 片桐昭彦著『戦国期発給文書の研究』 森田真一 |
(102) |
| 松尾正人著『近代日本の形成と地域社会 -多摩の政治と文化-』 伊藤暢直 |
(110) |
| 松尾正人著『木戸孝允』 大湖賢一 |
(116) |
| 久住真也著『長州戦争と徳川将軍 -幕末期畿内の政治空間-』 友田昌宏 |
(123) |
博物館・資料館探訪
第32号平成21年3月
公開講演
| 中世武士団はハイブリッドの新人類だった 入間田宣夫 |
(1) |
論文
| 渤海滅亡後の女真社会と地域間関係 ―「ニコラエフカ文化」の格子目状叩き土器をめぐって― 中澤寛将 |
(17) |
| 慶應義塾大学古文書室における古文書検索システムの構築 丸島和洋 |
(38) |
研究ノート
| 泰和六年(元久三・一二〇六)対馬島宛高麗牒状にみえる「廉察使」について 近藤 剛 |
(57) |
史料紹介
| 中央大学所蔵久世家文書「寛文三年日次」 「久世家文書」研究会 |
(71) |
書評
| 大村裕著『日本先史考古学史の基礎研究―山内清男の学問とその周辺の人々―』 小林謙一 |
(93) |
| 垣内和孝編『室町期南奥の政治秩序と抗争』 小国浩寿 |
(100) |
| 小山幸伸著『幕末維新期長崎の市場構造』 安高啓明 |
(106) |
| 松井秀明著『エピソードで語る日本文化史』上・下 飯塚 聡 |
(111) |
新刊紹介
| 小林謙一・セツルメント研究会編『縄文研究の新地平(続)―竪穴住居・集落調査のリサーチデザイン―』 井出靖夫 |
(120) |
| 田代和生著『日朝交易と対馬藩』 鈴木康子 |
(124) |
博物館・資料館探訪
第33号平成22年3月
公開講演
| 奥最後の歩兵奉行- 「太平年表録」を読む一 大口勇次郎 |
(1) |
論文
| 来日宋海商の廻却と廻却官符 河辺隆宏 |
(26) |
| 戦国期境目地域における在地領主の動向一上野国沼田地域と小川可遊斎を中心として一 大貫茂紀 |
(44) |
| 幕末期武家参内に関する空間的考察一諸大夫の間と仮建を中心に一 久住真也 |
(63) |
| 幕末の志士田中光顕と維新政権 松尾正人 |
(82) |
研究ノート
| 『出雲国風土記』異同一題- 「功鳥」と「悪鳥」をめぐって 佐藤 豊 |
(109) |
調査だより
| 2008年度神奈川県相模原市大日野原遺跡の発掘調査 永田 悠記・納 美保子・小林 謙一 |
(125) |
書評
| 小林謙一・国立歴史民俗博物館編『歴博フォーラム縄文時代のはじまり-愛媛県上黒岩遺跡の研究成果-』 山口欧志 |
(129) |
『白門考古論集2』編集委員会・中央大学考古学研究会編
『白門考古論叢III一中央大学考古学研究会創設40周年記念論文集-』 井出靖夫 |
(139) |
| 峰岸純夫・入間田宣夫・白根靖大編『中世武家系図の史料論』上・下巻 前嶋 敏 |
(147) |
| 峰岸純夫著『中世社会の-漢と宗教』 柳澤 誠 |
(155) |
落合功著『地域形成と近世社会一兵農分離制下の村と町-』
落合功著『近世の地域経済と商品流通一江戸地廻り経済の展開-』 宮坂 新 |
(164) |
| 岡崎寛徳著『改易と御家再興』 内野 豊大 |
(173) |
新刊紹介
| 小池上悟著『石造供養塔論致』 山口欧志 |
(182) |
| 森安彦編著『武蔵国多摩郡関前新田名主井口忠左衛門と御門訴事件』 井出靖夫 |
(186) |
| 藤野保著『江戸幕府崩壊論』 前嶋 敏 |
(188) |
博物館・資料館探訪
第34号平成23年3月
中央史学会第35回大会シンポジウム「アーカイブズの進展と歴史研究」
特別講演
| 伊藤博文の関係史料について 一ヨーロッパからの書簡を中心に一 鳥海 靖 |
(4) |
| 史料調査と歴史研究 一私の経験から一 宮地正人 |
(16) |
課題報告
| 外務省記録と外交史研究 熊本史雄 |
(33) |
| 宮内省公文書類と近代史研究 堀口 修 |
(54) |
討論
論文
| 『朝野群載』所収高麗国礼賛省牒状について-その署名を中心に一 近藤 剛 |
(81) |
| 天正14年の二本松「惣和」と伊達政宗 垣内和孝 |
(102) |
| 東京府における旧幕府関係史料類の収集・管理について 一明治10年代の庶務課記録科(掛)の動向を中心に一 岩橋清美 |
(118) |
研究ノート
| 1873年の日本・ペルー条約交渉 一領事裁判権撤廃問題をめぐって一 鈴木 祥 |
(134) |
調査だより
| 2009年度神奈川県相模原市大日野原遺跡の発 矢嶋良多・小林 謙一 |
(152) |
書評
| 峰岸純夫著『中世荘園公領制と流通』 柴崎啓太 |
(156) |
| 峰岸純夫著『中世の合戦と城郭』 片桐昭彦 |
(164) |
| 堀口修編著『明治立憲君主制とシュタイン講義』 佐藤元英 |
(172) |
| 西村敏也著『武州三峰山の歴史民俗学的研究』 早田旅人 |
(176) |
| 松尾正人編『中央大学図書館所蔵幕末・明治期名家書翰草稿一史料と研究-』 寺寄弘康 |
(185) |
博物館・資料館紹介
| しょうけい館(戦傷病者史料館) 奥平 晋 |
(191) |
第35号平成24年3月
小特集 災害と歴史研究
| 特集にあたって 『中央史学』編集委員会 |
(1) |
| 考古学における地震痕跡の研究 小林謙一 |
(2) |
| 貞観11年(869)の天災と外寇 石井正敏 |
(13) |
| 中世東国における地震と戦乱 峰岸純夫 |
(21) |
| 文化財救出と人文学の現場 ―長野県北部震災での経験から― 白水 智 |
(30) |
| 歴史資料保全活動のあり方 ―宮城歴史資料保全ネットワークにおける活動を通して― 白根靖大 |
(41) |
公開講演
論文
| 近世北信濃の地主小作相論と幕府代官 山崎 圭 |
(66) |
| 異国船の琉球来航問題と島津斉彬 岡部敏和 |
(84) |
| 明治時代の勲章制度 刑部芳則 |
(102) |
| シベリア出兵における日本陸軍の新聞操縦活動 藤田 俊 |
(125) |
| 昭和16年における陸海軍航合問題 ―山下視察団が総合問題に及ぼした影響― 山口 亮 |
(144) |
研究ノート
史料紹介
| 丹波国山国荘鳥居家文書の中世文書 ―宇津氏発給文書― 丹波国山国荘調査団 |
(185) |
調査だより
| 2010年度神奈川県相模原市大日野遺跡の発掘調査 矢嶋良多・小林謙一 |
(199) |
書評・紹介
| 坂田聡編『禁裏領山国荘』 高島良太 |
(203) |
| 清水紘一著『日欧交涉の起源』 安高啓明 |
(209) |
| 安高啓明著『近世長崎司法制度の研究』 吉岡誠也 |
(218) |
| 藤野保著『幕器制国家と明治維新』 寺島宏貴 |
(225) |
| 小林謙一著『発掘で探る縄文の暮らし 中央大学の考古学』 水田悠記 |
(234) |
小林謙一・工藤雄一郎・国立歴史民俗博物館編
『歴史フォーラム 縄文はいつから!? ―地球環境の変動と縄文文化―』 矢嶋良多 |
(239) |
| 刑部芳則著『洋服・散髮・脱刀一服制の明治維新』 清水善仁 |
(242) |
博物館・資料館探訪
第36号平成25年3月
公開講演
論文
| 近世後期川越郡代所在方支配の制度と特質一支配機構と支配慣行 北村厚介 |
(12) |
| 幕末期における長崎外国人居留地の運営と居留場掛 吉岡誠也 |
(30) |
研究ノート
| 廃藩置県にともなう行政文書の引渡し ―品川県を事例に― 篠崎佑太 |
(50) |
| GHQ歴史課陳述録の編集について ―オーラルヒストリーによる終戦史研究― 佐藤元英 |
(66) |
教育の現場から
| 日本史教育における「東アジア」と「冊封体制」 大西信行 |
(87) |
調査だより
| 2011年度神奈川県相模原市大日野原遺跡の発掘調査 矢嶋良多・小澤政彦・小林謙一 |
(103) |
書評
| 大村裕著『縄紋土器の型式と層位』 小林謙一 |
(110) |
| 友田昌宏著『未完の国家構想 ―宮島誠一郎と近代日本―』 宮間純一 |
(121) |
新刊紹介
| 坂田聡著『家と村社会の成立 ―中近世移行期論の射程―』 大貫茂紀 |
(128) |
| 山本英貴著『江戸幕府大目付の研究』 北村厚介 |
(133) |
| 松尾正人著『徳川慶喜一最後の将軍と明治維新』 佐藤愛未 |
(137) |
史料紹介
| 丹波国山国荘鳥居家文書の中世文書 ―宇津氏受給文書― 丹波国山国荘調査団 大其茂紀・柳澤 誠 |
(140) |
博物館・資料館紹介
第37号平成26年3月
公開講演
論文
| 年未詳五月十四日付源頼朝袖判御教書案について ―島津注と日宋貿易― 石井正敏 |
(23) |
| 中世後期の「頼母子」に関する一試論 熱田 順 |
(42) |
| 越後享禄・天文の乱と長尾氏・中条氏 前鳴 敏 |
(65) |
近世後期における旗本家の財政資金運用と知行所村の社会経済構造
―一四○○石旗本高家長沢氏の地頭所貸付金政策を事例に― 山崎和真 |
(80) |
| 幕末期薩摩藩の写真技術導入 川崎華菜 |
(99) |
| 文久期江戸城登城と国事周旋 ―鳥取藩主池田慶徳の動向を中心に― 篠崎佑太 |
(115) |
| 明治初年の日本・ハワイ条約交渉と条約改正問題 鈴木 祥 |
(136) |
| 占領期皇室財産処理の基礎的考察 奥平 晋 |
(154) |
昭和前半期までの竪穴住居跡覆士の調査方法
―「酒詰仲男調査・日録」を読み解く― 小林謙一 |
(199) |
史料紹介
丹波国山国荘鳥居家文書の中世文書
―名職・田地関係文書― 丹波国山国荘調査団 大貫茂紀・高島良太・柳澤 誠 |
(200) |
調査だより
| 2012年度神奈川県相模原市大日野原遺跡の発掘調査 小澤政彦・小林謙一 |
(221) |
書評
| 中澤寛将著『北東アジア中世考古学の研究一森・渤海・女真』 永田悠記 |
(227) |
| 刑部芳則著『明治国家の服制と華族』 清水善仁 |
(234) |
| 鳥海靖著『逆賊と元熱の明治』 橋上武史 |
(243) |
新刊紹介
石井正敏著『NHKさかのぼり日本史外交篇[8] 鎌倉「武家外交」の誕生
―なぜ、モンゴル帝国に強硬勢を貫いたのか』 近藤 剛 |
(252) |
| 佐藤孝之著『近世山村地域史の研究』 北村厚介 |
(257) |
| 尚友倶楽部・華族史料研究会編『四條男爵家の補維新と近代』 宮間純一 |
(261) |
| 佐藤元英著『御前会識と対外政略3』 田中悠介 |
(264) |
博物館・資料館紹介
第38号平成27年3月 森安彦先生古稀記念号
公開講演
| 海辺の村の近世 ―伊豆国君沢郡長浜村を事例として― 渡辺尚志 |
(1) |
論文
| 赤報隊像の変遷に関する一考察 岩立将史 |
(19) |
| 地租改正事務局の設置 滝島 功 |
(39) |
| 佐藤榮作内閣の公害対策 ―「経済開発」と「社会開発」の調和をめぐる葛藤― 新嶋 聡 |
(58) |
史料紹介
| 丹波国山国荘鳥居家文書の中世文書 ―送状・請取状― 丹波国山国荘調査団 大貫茂紀・柳澤誠 |
(78) |
調査だより
| 2013年度神奈川県相模原市大日野原遺跡の発掘調査 |
(97) |
書評
| 大村裕著『日本先史考古学史講義 ―考古学者たちの人と学問』 小林謙一 |
(103) |
| 西川広平著『中世後期の開発・環境と地域社会』 前嶋 敏 |
(110) |
| 坂田聡・吉岡拓著『民衆と天皇』 西川広平 |
(117) |
| 鈴木芳行著『首都防空網と〈空都〉多摩』 橋上武史 |
(125) |
新刊紹介
| 小林謙一・黒尾和久・セツルメント研究会編『縄文研究の新地平(続々)~縄文集落調査の現在・過去・未来~』 小澤政彦 |
(132) |
| 荒野泰典・石井正敏・村井章介編『日本の対外関係[2]律令国家と東アジア』 川嶋孝幸 |
(138) |
| 鈴木康子著『長崎奉行―等身大の官僚群像』 吉岡誠也 |
(143) |
| 落合弘樹著『敗者の日本史18西南戦争と西郷隆盛』 友田昌宏 |
(147) |
| 小林道彦著『児玉源太郎―そこから旅順港は見えるか』 藤田 俊 |
(151) |
博物館・資料館紹介
PAGE TOP